中小製造業が収益管理・採算管理を行えない本当の理由とは
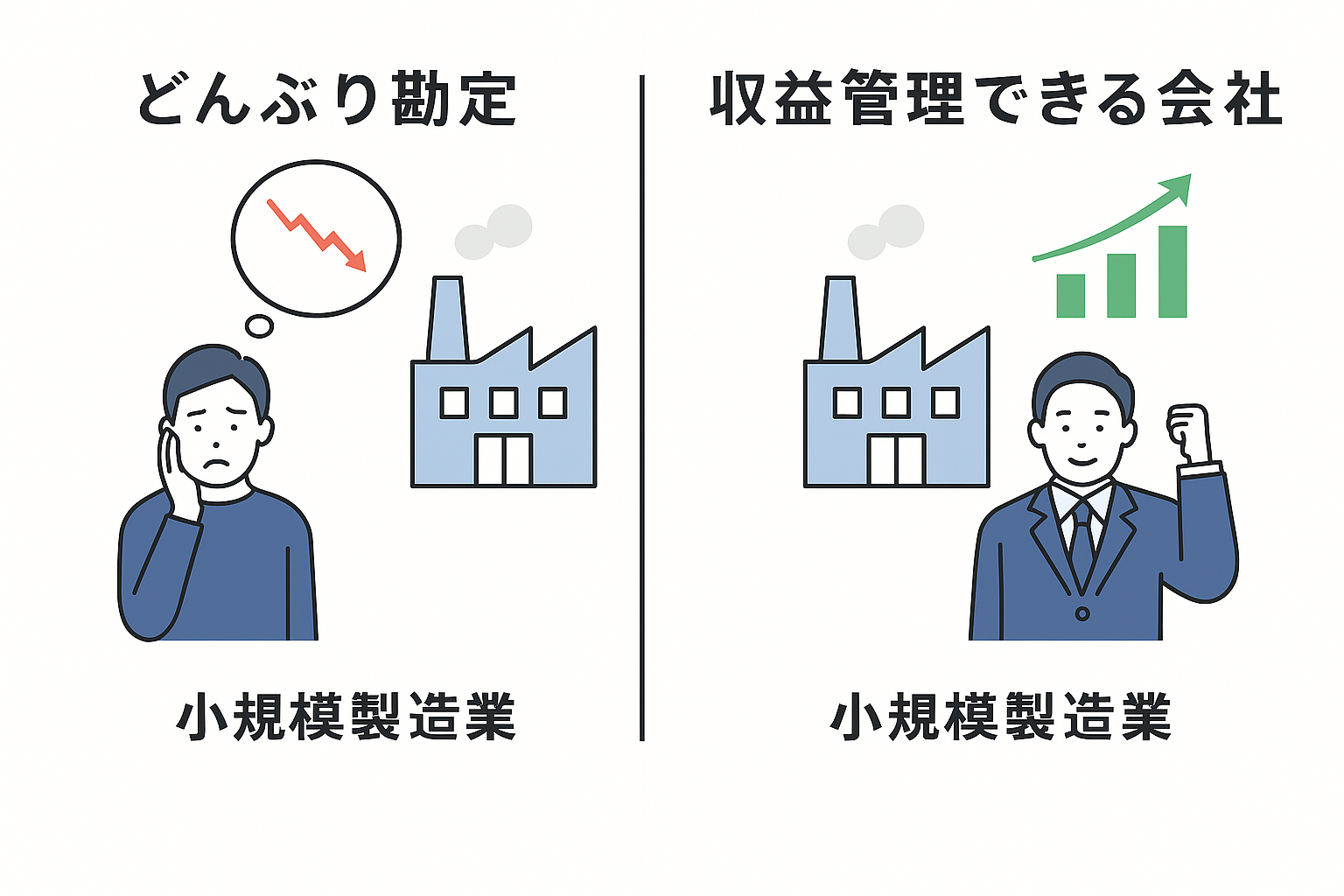
目次
中小製造業における「収益管理」の必要性
「忙しく働いているのに、なぜかお金が残らない」。これは多くの中小製造業の経営者が抱える共通の悩みです。売上は立っている。受注もある。なのに、利益が思ったほど出ていない。こうした問題の背景にあるのが、「収益構造が見えていない」ことです。
製造業の現場では、材料費や外注費などの“原価”はある程度把握されていることが多いものの、「本当に儲かっているのはどの製品か」「赤字になっている受注はどれか」といった問いに、即答できる会社は多くありません。利益が見えないまま受注をこなし続けてしまい、結果として“儲からない忙しさ”に陥っているケースが少なくないのではないでしょうか。
そもそも、中小製造業が採算管理にまで手を回せないのには理由があります。経営者が現場にも深く関わっており、業務の多くが属人的に進められていること。会計ソフトが出力した試算表は「会社全体の損益」を示していても、「製品別」「顧客別」「受注別」といった細かい収益性までは把握できないこと。そして、そもそもその必要性を「実感できるタイミングがない」ことも一因です。
しかし、こうした状態を放置していると、いくら仕事があっても利益が残りません。さらに問題なのは、赤字受注を繰り返していることに気づかず、経営体力をじわじわと削ってしまうリスクです。
収益管理を行うことで経営改善のヒントが生まれる
一方で、収益管理の視点を取り入れることで得られるメリットは非常に大きなものです。たとえば、見積と実績のコストを比較して差異を可視化することで、「この製品は想定より工数がかかっている」「この顧客は発注は多いが利益率が低い」といった、経営改善のヒントが浮かび上がります。経営者にとっても、「値上げ交渉の根拠」や「受注の優先順位付け」といった判断がしやすくなりますし、現場の社員にとっても、「自分の作業が利益にどうつながっているのか」が実感できるようになります。
また、現在ではデジタルツールやクラウドシステムの進化により、こうした収益管理を“現場の延長線上”で行える仕組みも整ってきました。IT導入補助金や各種DX支援策の活用も視野に入れながら、経営数字をリアルタイムで把握できる環境を整えることが、中小製造業の生き残りにおいてますます重要になっています。
収益管理とは、単なる数字の記録ではなく、「どこで利益が生まれ、どこで失われているか」を把握し、戦略的に動くための“経営の羅針盤”です。売上至上主義から脱却し、「利益で考える経営」へと舵を切る。そのための第一歩が、まさにこの“収益の見える化”です。
中小製造業が収益管理を行えない8つの理由
中小製造業の経営支援に携わる中小企業診断士やコンサルタントの方であれば、収益改善や価格交渉の支援を行う際に、一度は以下のような声を耳にされたことがあるのではないでしょうか。
理由1.作業実績の収集がされていない、できない
製造原価の中で最も見落とされがちなのが、労務費や設備費の算出に必要な作業時間の記録です。材料費や外注費は明確でも、作業時間を日報などで記録、蓄積している会社はごく一部です。現場に負担をかけたくない、どうせ見ないから、などの理由で、そもそもデータがない、もしくは、あっても集計していない。
理由2.原価計算の考え方が整理されていない
製造原価、見積原価、実績原価…それぞれの定義や計算方法を正確に理解していないケースも多く、勘と経験で見積もりを出しているケースが大半ではないでしょうか。感覚的な見積もりでは、利益を確保できない仕事を繰り返している可能性があります。また、そのような状態では、価格交渉の際に論理的な説明をすることはできません。
理由3.データがバラバラで、仕組みがない、統合されていない
帳票が紙、Excel、業務システムと分散しており、一元管理できるインフラが整っていないのも大きな課題です。こうした状態では、データを収益管理に活かすどころか、集計すら大仕事になってしまいます。
また、販売管理システム、受発注システム、原価管理システム、顧客管理システムは導入しているが、統合されておらず別々に稼働しているケースも多々見られます。このような状態の問題は、それぞれにマスタが存在することです。更新漏れがあったりするとどれが最新なのかわからない状態になります。収益管理の観点からは、販売管理もしくは受発注システムと原価管理システムが統合されていないことが問題です。受注データと原価データが紐づいていなければ、案件ごとの収益を管理することができないからです。
理由4. 経営者が“勘と経験”で判断している
長年の経験から、数字に頼らずとも問題のある案件は察知できる。その感覚こそが落とし穴になる場合もあります。数字で見える化する必要性が社内に浸透しません。ざっくりな見積りをしていても仕事がたくさんあり、引手あまたの状況であれば問題なかったかもしれません。
業界全体として仕事量が減少しており、材料費や賃金が上昇している昨今の状況では、会社の収益構造を把握した上でレート設定を行い、精度の高い見積を作成することが必要になっています。
また、事業承継の観点からも、社長やベテランの勘や経験に頼る状況ではなく、会社としてルールを設定することが必要になるかもしれません。FactoryAdvanceなどの業務管理システムの導入は、ルール決めをするという観点でも有効な方法だと考えます。
FactoryAdvanceを導入することで、見積作成ルール、発注ルール、在庫管理ルール、手配管理のルール、実績管理のルール、予実管理のルール、課題抽出の仕組みなどを整理することが可能です。
理由5. 数字が見えると“都合が悪い”心理的抵抗
収益管理ができるようになると、儲かっていない製品や不採算な工程が明らかになります。それが現場の責任と結びついたり、営業活動に影響する恐れがあるため、「見ないほうが楽」と感じる心理的なブロックが働きます。
この辺りは非常に繊細なところではありますが、赤字体質を改善して高収益企業を目指すとなると、そんなことも言ってられないと思いますがいかがでしょうか。
理由6. 誰も“自分ごと”として捉えていない
収益管理は部門横断で取り組む必要がありますが、誰か一人の役割だと思われがちです。社内で「収益を見える化することが重要だ」という共通認識がない限り、仕組みは形だけになってしまいます。
上手くいっている会社は、人事生産性とボーナスを紐づけるなどの仕組みを採用しているところもあるようです。
日経ビジネス賃上げの研究第6回「債務超過に陥った花屋が「人時生産性」で大復活」
理由7. 小ロット多品種=分析しても無駄という思い込み
人事生産性とボーナスを紐づけた例が日経ビジネスに紹介されていましたのでご紹介させていただきます。
毎回条件が違っても、利益構造の傾向を把握することは可能です。少量でも分析すれば「次の一手」は見えてきます。場合によっては、かなり少額の取引があるかもしれません。そんな少額のために分析しても意味がないと思われるのも無理はありません。ただ、その少額取引の人事生産性(時間あたりの付加価値)がとんでもなく高いかもしれません。そうだとしたら、数量を増やす事でかなりの粗利を稼ぐことができるシンデレラ製品なのかもしれません。やはり、どんな取引でも分析してみる意味はあると思います。
理由8. 生産管理システムの導入がゴールになっている
目的が不明確なまま導入してしまうと、「とりあえず生産管理システムを導入したけど使われていない」状態に陥ります。生産管理などのシステムは導入することが目的ではなく、経営判断や現場改善につなげて初めて意味を持ちます。国や自治体がDX化を推進しているた、補助金があるのでとりあえず導入したという話をよく聞きます。何のために生産管理システムを導入を行うのかしっかり検討する必要があります。
生産管理システムを検討する際に、いきなり必要な機能の検討を始めるのではなく、経営方針や経営課題を議論した上で、どのような機能が必要となるのか検討し、最適なツールを導入することをおすすめします。経営を考える上では、収益の管理は最重要事項になります。したがって、製造業においては、生産管理システムを導入する際には、収益管理ができることが重要になります。
FactoryAdvanceでは、どのように収益管理ができるのか?
FactoryAdvanceは、受注ごとに利益を見える化し、改善アクションにつなげる“収益管理の仕組み”を内蔵した実践型ツールです。
1. 見積段階で「利益が出るか」を試算できる
2. 受注ごとに「予定と実績の差異分析」ができる
3. 改善サイクル(見積→実績→分析→課題抽出→改善)を回せる
4. 現場でも使いやすいUIと機能設計
5.専門家による伴走支援で経営改善を進められる
収益構造を数字で把握し、経営判断や改善アクションにつなげる。そのための仕組みを“現場レベル”で実現できるのが、FactoryAdvanceの強みです。
まとめ|収益管理が「できない」のではなく、「できる仕組み」がないだけ
中小製造業が収益管理ができていない理由は、データがない、意識がない、仕組みがない。この3つに集約されます。FactoryAdvanceを活用することで収益管理の仕組みを構築することが可能です。
また、FactoryAdvanceを活用した収益改善に向けたを、中小企業診断士や製造業専門のコンサルタントが伴走してつくることも可能です。
中小製造業の収益管理方法については、中小製造業向け収益管理実践ガイドをダウンロードしてご参照ください。
投稿者プロフィール

- 株式会社イーポート代表取締役 ITコーディネーター/キャッシュフローコーチ
- FactoryAdvanceの開発販売を通して製造業の収益改善・DX推進に貢献したいと思っております。中小製造業の企業価値を高めるプラットフォーム「FACTORY SEARCH」の運営も行っています。プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年11月30日「製造業X」とは?中小企業が直面する変化と勝機
- 2025年7月3日中小製造業のためのデジタルマーケティング入門
- 2025年6月15日今日から使える!中小製造業のChatGPT・Gemini活用術7選
- 2025年5月28日焼入れ専門業に最適な生産管理システムとは?
